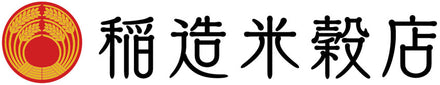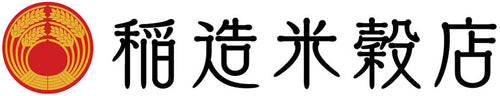天日塩と塩化ナトリウムの違いが、なんだってんだ!?え!
2022年2月23日
日本の高級和食店の場合、「○○塩を使用」とはいちいち謳わない。
値段ありきの大衆店ではないし、板前だって
「いやな奴は食わなきゃいい」
みたいな、見た目は謙虚を装いつつも、(まるで稲造のような)生意気な態度でw作りたいものを作るだろう。
ゆえに、調味料の王者たる「塩」には、特にこだわっているのではないか。
(星州の超高級店はどうだろう?)
「美味しさ」とは、店構えや評判、あるいは器などで演出されるプラセボ効果、あるいはハロー効果や価格効果などの総合演出。
(※ワインだと、
「一流の醸造家が丹精込めた、1本〇〇万円のボルドー産」
なんて先入観があると、飲む前からゴリゴリ期待しちゃう。味とは、舌より、脳で感じるもの。
実際、目隠しして飲んだら、ほとんどの日本人は1本1480円の大衆ワイン(フランスだと1本300円とか)と区別できなかったりするらしい)
といっても、舌は正直。ちゃんとした料理というのは、和食味付けの肝たる塩味に、角やしつこさがない。
まろやかで、すぅ~~っと自然に血液になじむというか、そういう美味しさってありますよね?
あれって、やっぱり塩を選んでいるから。
「いや、うちは普通に99.9%塩化ナトリウムの精製塩ですよ。
それに、昆布やカツオからダシとるなんか面倒だし高いから、味の素で一流の味は出せるんです!
要は、料理の腕より、インスタ映えして、店構えと器で客の脳をだまして錯覚させることなんスよ!」
なんてホリエモン風のオーナーもいるのだろう。しかし、丁稚から叩き上げたガンコ板前なら絶対、包丁と、そして塩は選ぶ。
〇
実際、海の天然塩はちがう。
たとえば、炒め物に小さじ一杯とか使ってみる。
精製塩だと塩っ辛さが料理全体を覆ってしまうが、海の天然塩は、具材の持ち味を邪魔しない(あるいは引き出す)しょっぱさ、というのか。
なじみがいい。そう、そういう表現。精製塩は、塩単独では浮いちゃうから、余計に砂糖を入れたりする。
精製塩は「イオン交換膜法」といって、海水から塩素とナトリウム「だけ」を抽出するため、塩化ナトリウム99.5~99.9%。
一方、海の天然塩の塩化ナトリウム含有率95%以上で、残り5%にカリウム、カルシウム、マグネシウムをはじめ、鉄、リンといった微量栄養素も含む。
天然塩はまさに「海の結晶化」だから、そういう料理になる。
実際、天然塩に慣れると舌だけは贅沢になる。
稲造は見た目が貧乏で、実は本当に貧乏なんですがw、たまに外食すると味が濃く感じられて、外食が苦手になった。
脂っこいと、胃モタレするような年になったせいもあるだろうけど。
・・・
ははうえさま、お元気ですか
ド田舎の濃い味に慣れたわたしの舌は、海の天然塩のおかげで、すっかり角の取れた上品な塩味に慣れてしまったようです。
それではまた、おたよりします。ははうえさま、稲造~♪
〇
この3月上旬。石川は能登半島の珠洲(すず)から、その海の天然塩が本邦初上陸いたします。
能登といえば、日本海側のポコッと突き出たあそこ。知る人ぞ知る、江戸時代からの塩の名産地です。
まず、遥か間宮海峡から南下してくる寒流の「リマン海流」と、対馬から北上してくる暖流の「対馬海流」の合流点にて、海そのものが豊か。
地理的には、絢爛豪華な(?)金沢文化圏とは途絶した、秋田以上の超ド田舎。
縄文時代からほとんど変わらぬ、開発から完全に取り残された永遠の過疎地。排水する工場はおろか、住宅すらまばら。
そもそも、「珠洲」なんて誰も読めない。
要するに、能登沖は海そのものが豊かで、かつ、すげ~綺麗なんです。
南国の島々は、コバルトブルーで熱帯魚なんか泳いて、ビキニのおねぇちゃんがキャッキャしてそうな華やかなイメージ。
一方、日本海はですね…
岩礁だらけで、冬は暴風雪の津軽海峡冬景色そのままで。
凍えそうなカモメが一羽飛ぶ下で、生活と男に疲れ切った場末のスナックのママが、かじかんだ手をこすりあわせている。
そういう暗さが漂っているんですよ。都会育ちの人、想像できます?ガチ暗いでしょ?ww
でも、ディープブルーの海は見た目も中身もきれい。
和食にはそんな日本海の塩だ!と、使ってみて納得した能登の塩を、店頭に並べてみたくなりました。
〇
珠洲の塩は天日平釜法。人力100%、機械化合理化の気配まったくなしw
秋田、石川、富山は「美人が多い」といわれます。低紫外線量トップ3県で、顔だちどうこうより、七難隠す色白な人が多いからです。
製塩には、海水から水分を飛ばして濃縮する過程があります。上記のような地域柄なので、太陽光だけで乾燥させるのは無理。
ということで、これも江戸時代からそのまま、立てかけた簾(すだれ)に海水を振りまき、滴ってくる過程で水を自然(天日)蒸発させます。
その濃縮海水を「平釜」という文字通りの巨大な平釜で、しかも薪で煮込む。完全蒸発させて底に残ったものが、まさに海の結晶=天然塩です。
岩塩に比べて2/3~半分くらいのしょっぱさ。(岩塩にはミネラル成分が少ないため)
塩むすびで試してみると、違いがはっきりするレベル。ほんのりと甘みさえ感じるしょっぱさだから、
「おかあさん、おしおかえた?」
ってわかる子には絶対わかる。
塩も使い分け。洋食には洋食らしく岩塩や欧州の海塩。繊細な和食にはやっぱり、日本の海の天然塩がふさわしい。
〇
一時帰国された時、百貨店等で天然塩を吟味して少量購入、シチュエーションに応じて使い分けてみると、絶対面白い。
「なんか変わった!」
って家族にバレるくらいおかずのレベルが上がる分、お米ももっと美味しくなる。
で、稲造米をいっぱい買ってもらえれば…なんて下心ムンムンww
同じ料理でも塩次第で違ったものになるって、面白くないですか?発見があって、学ぶこともあって。
「外食って濃いな~」
みたいに、町人のくせに舌だけは貴族になってしまうw
で。
これが塩麹だと、成分がより複雑化して、さらに奥行きがでます。次回また。
日本の高級和食店の場合、「○○塩を使用」
値段ありきの大衆店ではないし、板前だって
「いやな奴は食わなきゃいい」
みたいな、見た目は謙虚を装いつつも、(まるで稲造のような)
ゆえに、調味料の王者たる「塩」には、
(星州の超高級店はどうだろう?)
「美味しさ」とは、店構えや評判、
(※ワインだと、
「一流の醸造家が丹精込めた、1本〇〇万円のボルドー産」
なんて先入観があると、飲む前からゴリゴリ期待しちゃう。
実際、目隠しして飲んだら、
といっても、舌は正直。ちゃんとした料理というのは、
まろやかで、すぅ~~っと自然に血液になじむというか、
あれって、やっぱり塩を選んでいるから。
「いや、うちは普通に99.9%塩化ナトリウムの精製塩ですよ。
それに、昆布やカツオからダシとるなんか面倒だし高いから、
要は、料理の腕より、インスタ映えして、
なんてホリエモン風のオーナーもいるのだろう。しかし、
〇
実際、海の天然塩はちがう。
たとえば、炒め物に小さじ一杯とか使ってみる。
精製塩だと塩っ辛さが料理全体を覆ってしまうが、海の天然塩は、
なじみがいい。そう、そういう表現。精製塩は、
精製塩は「イオン交換膜法」といって、
一方、海の天然塩の塩化ナトリウム含有率95%以上で、残り5%
天然塩はまさに「海の結晶化」だから、そういう料理になる。
実際、天然塩に慣れると舌だけは贅沢になる。
稲造は見た目が貧乏で、実は本当に貧乏なんですがw、
脂っこいと、
・・・
ははうえさま、お元気ですか
ド田舎の濃い味に慣れたわたしの舌は、海の天然塩のおかげで、
それではまた、おたよりします。ははうえさま、稲造~♪
〇
この3月上旬。石川は能登半島の珠洲(すず)から、
能登といえば、日本海側のポコッと突き出たあそこ。
まず、遥か間宮海峡から南下してくる寒流の「リマン海流」と、
地理的には、絢爛豪華な(?)金沢文化圏とは途絶した、
縄文時代からほとんど変わらぬ、
そもそも、「珠洲」なんて誰も読めない。
要するに、能登沖は海そのものが豊かで、かつ、すげ~
南国の島々は、コバルトブルーで熱帯魚なんか泳いて、
一方、日本海はですね…
岩礁だらけで、冬は暴風雪の津軽海峡冬景色そのままで。
凍えそうなカモメが一羽飛ぶ下で、
そういう暗さが漂っているんですよ。都会育ちの人、
でも、ディープブルーの海は見た目も中身もきれい。
和食にはそんな日本海の塩だ!と、
〇
珠洲の塩は天日平釜法。人力100%、
秋田、石川、富山は「美人が多い」といわれます。
製塩には、海水から水分を飛ばして濃縮する過程があります。
ということで、これも江戸時代からそのまま、立てかけた簾(
その濃縮海水を「平釜」という文字通りの巨大な平釜で、
岩塩に比べて2/3~半分くらいのしょっぱさ。(
塩むすびで試してみると、違いがはっきりするレベル。
「おかあさん、おしおかえた?」
ってわかる子には絶対わかる。
塩も使い分け。洋食には洋食らしく岩塩や欧州の海塩。
〇
一時帰国された時、百貨店等で天然塩を吟味して少量購入、
「なんか変わった!」
って家族にバレるくらいおかずのレベルが上がる分、
で、稲造米をいっぱい買ってもらえれば…なんて下心ムンムンww
同じ料理でも塩次第で違ったものになるって、面白くないですか?
「外食って濃いな~」
みたいに、町人のくせに舌だけは貴族になってしまうw
で。
これが塩麹だと、成分がより複雑化して、さらに奥行きがでます。
タグ: